こんにちは。小学生と幼稚園児の息子2人を育てているワーキングマザーhoshiko(ほしこ)です。このブログでは主に、発達障害と思しき(ADHDの疑い)小学生の長男についてつづっていきたいと思います。

「支援級ってどんな子がいくところなの?」息子の質問に驚いた
毎日楽しそうな息子をみて、転籍してよかったと思う
小3になって教室を飛び出す、板書をしないなど、問題行動が増えてきた息子。「教室にいると死にたくなる」という発言もあり、小4から支援級へ転籍しました。
支援級転籍までの経緯はこちらの記事をチェック
-

教室にいられない…特別支援学級をすすめられて
こんにちは。小学生と幼稚園児の息子2人を育てているワーキングマザーhoshiko(ほしこ)です。このブログでは主に、発達障害と思しき(未診断)小学生の長男についてつづっていきたいと思います。 息子は発 ...
続きを見る
転籍前はいろいろ心配もしましたが、新しい学級ではとても楽しそうに毎日を過ごしています。
今まで学校までの足取りが本当に重く(歩くのも遅いけど)、校門をくぐってから教室に入るまでも非常に時間がかかっていました。あっちへウロウロしたり、こっちへウロウロしたり、花壇へ行ったり、職員室をのぞいてみたり…なかなか下駄箱にも入れませんでした。でも、支援級に転籍してからはスタスタと校門に入り、あっという間に下駄箱をくぐり、教室へ…という生活に様変わりしました![]()
教室を飛び出し、行く当てもなく、よく保健室を訪れていたのですが、それもめっきりなくなりました(養護教諭にお会いしたとき教えてくれました)。息子に「最近、保健室行かなくなったらしいじゃん。どうして?」と聞いてみたところ、「行く必要がないからだよ」と教えてくれました。
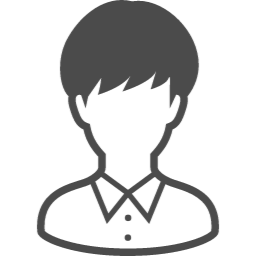
息子からそんな話を聞けるとは夢にも思っていなかったので、その言葉を聞けただけで転籍してよかった!と思いました。
朝の会や帰りの会のほか、交流といって4年生のクラスに社会や理科、音楽、図工、体育といった教科は受けに行くので、その時間はやはり気は進まない様子ですが、以前のように居場所のないところでずっと過ごさなければいけないという苦行から解放されて、なんとか自分の中で折り合いをつけつつやっているようです。
支援学級にいる子どもたち

息子の小学校の特別支援学級は、障害の特性に沿って「知的」「情緒」「身体虚弱、弱視、難聴」の3つの学級編成があります(そのほかに通級指導教室もあります)。息子は情緒級に在籍しているのですが、支援級全体でやる活動も多く、息子は学級の垣根を明確に理解しているわけではありません。
参考
■特別支援学校
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)を対象としている。幼稚部、小学部、中学部及び高等部が置かれる。
■特別支援学級
障害のある児童生徒のために小・中学校に置かれる学級であり、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。
■通級による指導
小・中学校の通常の学級に在籍している障害のある児童生徒が、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態であり、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などを対象としている。
厚生労働省:特別支援教育の概要
ある日、息子がこんなことを言いました。
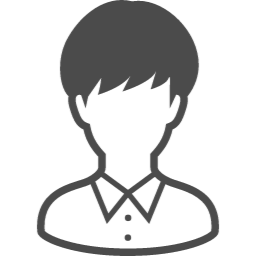
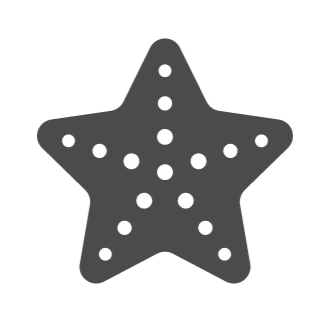
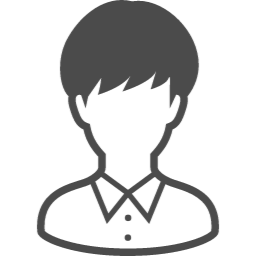
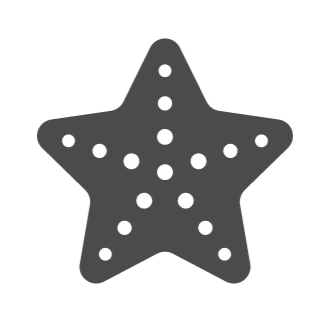
息子は「ふーん」という反応でしたが、事情がある子たちが集まっている学級であること、自分も苦手があるから、同じように苦手がある子がいるクラスというのをなんとなく理解したようでした。何気なく聞かれた質問でしたが、まさにインクルーシブ教育な質問だなと思います。通常級にいたら気づけないことに息子は気づいたのだと思います。ぜひ得意なことは自分がカバーしてあげる、苦手なことは手伝ってもらうという共存が支援級で学べたらいいなと思っています。




